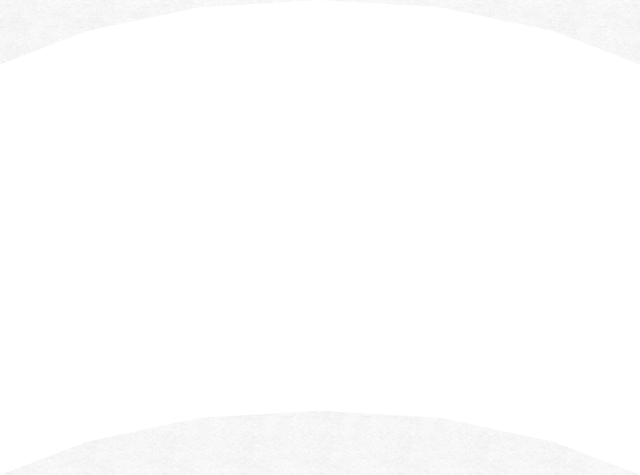「魚河岸」は日本橋と江戸橋の間、日本橋川の北岸に沿って、本船町から本小田原町一帯(現在の日本橋本町1丁目、日本橋室町1丁目)にあった魚市場。17世紀の初めに開設され、1935年に築地市場への移転が完了するまで300年以上にわたって、江戸と東京の人びとの食生活を支えつづけた。
市場への集荷は江戸の近海をはじめ、房州・上総・下総(千葉県)、相州(神奈川県)、遠州・豆州(静岡県)などの海の魚や淡水の魚が集められ、江戸の住人-武士と町人たちの腹中におさまった。
最初に魚市場を開いたのは、江戸幕府を開いた徳川家康に従って大坂から江戸に移住した森孫右衛門一族とその配下の漁民たちだった。彼らは幕府や大名に鯛※などの御用魚を優先的に納めるかわりに、残余の魚介類の市中商いの許可を得たと言われている。また森一族の後から魚河岸で開業した大和屋助五郎は、駿州(静岡県)の漁民に仕入金を貸し付け、海中に簀囲いをした活鯛場を設置させて、幕府や大名家の活鯛御用を大量受注し、有力魚商となった。
※鯛はめでたい魚の象徴として、日本人に愛され、珍重されてきた。
17世紀初頭、江戸の人口は15万人に達して魚介類の大きな需要が生まれていた。さらに18世紀に入ると江戸は人口100万人を超える巨大都市となり、魚河岸も大きく発展した。18世紀前半の記録によると、魚介類の問屋・仲買・販売業者数は本船町組・本小田原町組・本船町横店組・按針町組の4グループ500名にも増えていた。
幕府の御魚御用を務めることは魚商人として名誉なことだったが、その一方では代金が市中相場よりかなり安く、扱うたびに損失が嵩んだ。大ぶりの高級魚「鯛」でも、幕府への上納価格は、市中価格の5~6分の1に過ぎなかった。そこで魚河岸の問屋仲間は幕府に損失補填を願い出て、18世紀の初めには、日本橋・神田・四谷・赤坂など11か所の助成地を給い、その地代収入で損失の補填とした。
17世紀前期の魚河岸の様子は『江戸図屏風』に、19世紀前半の様子は江戸の地誌『江戸名所図会』に描かれている。朝夕、大量かつさまざまな魚介が荷揚され、店頭に並び、威勢良く取引された。『江戸名所図会』に見えられる魚を陳列している戸板状の台は「板舟」と言い、多くは有力商人が所有していた。「板舟」は一枚ごとに販売権が付帯しており、これを一枚から数枚借りて商いをする小規模商人も多かった。この板舟ははじめ河岸地の露天に設けられたが、市場の発展に従って河岸通りに魚を貯蔵する納屋が建つと、その納屋庇下を使用するようになり、さらに本船町から本小田原町までの店前街路を占用した。
魚河岸は日本橋地域に1656年まであった「吉原遊郭」や1842年まであった「歌舞伎小屋」の堺町・葺屋町(現在の日本橋人形町3丁目界隈)とともに「一日千両※」と称された江戸随一の繁華な一角で、屋敷は間口一間(約1.8m)奥行20間(約36m)につき千両もの高値がついた。
※両は江戸時代のお金の単位。時代によっても異なるが、1000両は約1億3000万円相当。
魚河岸の有力問屋は、豊富な資金力を用いて、歌舞伎・書画・浮世絵・俳諧など江戸文化のスポンサーとなったり、身内から多くの学者や文化人を輩出したりした。世界的に有名な俳諧師「松尾芭蕉」の経済的援助者で、芭蕉の門人の杉山杉風は御用魚問屋鯉屋市兵衛だった。
魚河岸は日本が近代国家になってからも存続して東京人の食卓に全国の魚介類を集荷・供給していたが、1923年の関東大震災の被災を契機に、東京改造計画で築地への移転が決まった。しかし、日本橋を去ることに反対する人が多く、移転完了には決定から10数年を要した。